2月4日(火)
4年生は体育館で「川上っ子なわとび大会」を行いました。
まずは、個人戦。前跳び一拍子2分15秒、後ろ跳び1分30秒、あや跳び1分、交差跳び45秒、二重跳び30秒に挑戦です。跳び切った人数がクラスの得点になるため、みんな一生懸命に取り組みました。結果は36対32で4年松組が勝ちました。また、3人の児童が5種目全てを跳び切るパーフェクト賞に輝きました。
次は、団体戦。4分間の8の字ジャンプで競いました。どちらのクラスも息を合わせてリズムよく跳んでいきました。結果は209回跳んだ4年松組の勝利でした。個人戦、団体戦ともに勝てなかった4年竹組は非常に悔しい結果となりましたが、「この悔しさを次の5年生にぶつけたい。」と次につなげている児童の姿もありました。


2月3日(月)に、地区別児童会が行われました。
今回の会では、3学期の登下校についての振り返り、新役員の選出、新年度の通学班の編成を行いました。
新年度の通学班の編成では、保護者の方にもご参加いただき、新1年生を含めた班について話し合いました。
班編成が終わった際には、1年間安全に通学できるようリーダーシップを発揮した6年生の班長さんに、みんなで感謝の気持ちを伝える場面も見られました。


新しく編成した班での通学が始まるのはもう少し先のこととなりますが、引き継いだ後も安全に通学できるようにみんなで頑張っていきます。
ご参加、ご協力いただきました保護者の皆様、誠にありがとうございました。
2年生は、生活科の学習で動くおもちゃを作っています。
一度完成したおもちゃですが、さらに動くように改良を続けています。


子どもたちは、より動くように、材料を変えてみたり、使う材料の数を増やしてみたりして、試行錯誤しながら頑張っています。


子どもたちが作るおもちゃがどれくらい動くようになるのか、すごく楽しみです。
1月29日(水)の5校時に、5年竹組の算数科「割合のグラフ」の研究授業が行われました。輸入品の種類と割合のグラフから読み取れることを、2学期に学習した「割合」の式に当てはめながら考えました。




「ことりタイム」(ペアでの話合い活動)では、自分と友達の考えの同じところや違うところを比べながら聞き合っていました。また、なぜそう考えたのかについて理由もしっかり述べていました。
資料の読み取りや比較は、今後の学習や生活において大切になります。今日の学習を通して、これからも身近な事象について関心を持ったり、疑問を広げたりしてほしいと思います。
4年生は図画工作科で「つくって・つかって・たのしんで」に取り組んでいます。板を自由に切って、動物や鳥などをイメージしたメッセージボードに仕上げていきます。
のこぎりを使って板を切ることは初めてのため、最初は苦戦しました。しかし、友達と協力して切っていくことで要領をつかみ、だんだんと上手に切ることができるようになりました。


これからも、のこぎりの使い方に気を付けて、安全に作っていきたいです。
1月10日(金)に3年生が、体育館で書き初め会を行いました。
冬休みの練習の成果を生かしながら、みんな集中して取り組みました。


「とめ」や「はらい」など、いろいろな筆の運び方に気を付けながら「友だち」という文字を書きました。
できあがった作品を満足げに見ている児童がたくさん見られました。
1月23日(木)、5年生が坊っちゃん劇場でミュージカル「KANO~1931甲子園まで2000キロ~」を観劇しました。
日本統治下での台湾を舞台に、民族の壁を越えて甲子園を目指す球児たちの物語です。1931年、夏の甲子園で準優勝を果たした台湾代表の高校を基にしています。

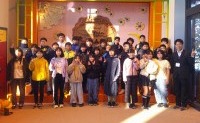
プロの役者の方々の演技を観て子どもたちは、「演技や歌声に迫力があった」、「場面が移るときの準備が素早かった」、「6年生を送る会の演出に生かしたい」などの振り返りをしていました。
2年生は、3学期に入ってから、九九検定に取り組んでいます。
冬休みにたくさん練習してきたこともあり、すらすらと読んでクリアしていきます。


2年生が終わるまでに、全員合格を目指して頑張っています。
本日の昼休み、なわとび大会団体戦を実施し、学級のみんなで「8の字ジャンプ」を跳びました。2学期の終わりから今日まで、どの学級も一生懸命練習に励んできました。他の学年が跳んでいる姿を見て、応援や拍手をしたり、自分たちの頑張りをたたえたりしていました。




温かい雰囲気の中、体育委員のスムーズな進行によってなわとび大会団体戦を実施することができました。一人一人の頑張りがみんなの心を一つにしていましたね。今日の学びを是非これからの学校生活に生かしてほしいと思います。
1月16日(木)に、3年生が防災教室(手つなぎ防災ひろば)を行いました。
今回の防災教室では、「いつ起こるか分からない災害に備えて知識や技術を学ぶことで、防災に対する意識を高める」ことを目的に、防災講座、非常食試食体験をしました。
防災講座では、災害時には身の危険を感じた際には、早めに安全な場所に避難することが大切であることを教えていただきました。そのためには、住んでいる地域をよく知っておくこと、もしものときのために非常持ち出し袋を備えておくとよいことも話していただきました。


また、ハイゼックス袋を使ったご飯の作り方や非常持ち出し袋に準備しておくとよい物を紹介していただいたり、避難所で使われる段ボールベッドで体を休める体験などをさせていただいたりしました。
非常食の試食体験では、東温市赤十字奉仕団の皆さんが朝早くから準備してくださったハイゼックス袋を使って炊いたご飯と東温市から提供していただいた非常食セットの中のレトルト食品のおかずを食べさせていただきました。初めて食べた子どもが多かったのですが、あちらこちらで「おいしい」「もっと食べたい」などの声が上がっていました。


いつ起こるか分からない災害に備えて、「自分の家でもきちんと備えをしておきたい」という感想を持った子どももいました。
体験したことを生かしながら「自分の命を自分で守ることができる子ども」が増えるように、これからも子どもたちと共に防災について学んでいきたいと思います。
今回の防災教室開催のためにご尽力いただいた、日本赤十字社愛媛県支部、東温市赤十字奉仕団、東温市市民福祉部社会福祉課、学校運営協議会委員の皆様、誠にありがとうございました。
5年生は、5時間目に「SOSの出し方に関する授業」を行いました。
まず、養護教諭から事前に行ったアンケートの結果を聞き、自分たちがどんな悩みを持っているか、悩みがあるときは誰に相談しているかについて確認しました。
次に、公認心理師の先生による「自分も相手も大切にするコミュニケーション、ストレスへの対処」についての講演を聞きました。講演を聞く中で、具体的なSOSを出して助けを求めることや、SOSを出せる相手を見つけることの大切さを学びました。
授業の最後には、東温市保健師の方から、不安や悩みがある場合の相談窓口の紹介がありました。




子どもたちが成長していく過程で、勉強や人間関係など、様々な不安や悩みが生まれてくると思います。自分一人で抱え込むのではなく、周りに相談することで、明るい気持ちで学校生活を送ってほしいと思います。